【本棚を探索】第6回『この30年間の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』高橋源一郎・斎藤美奈子 著/三宅 香帆
文学にできることを問う
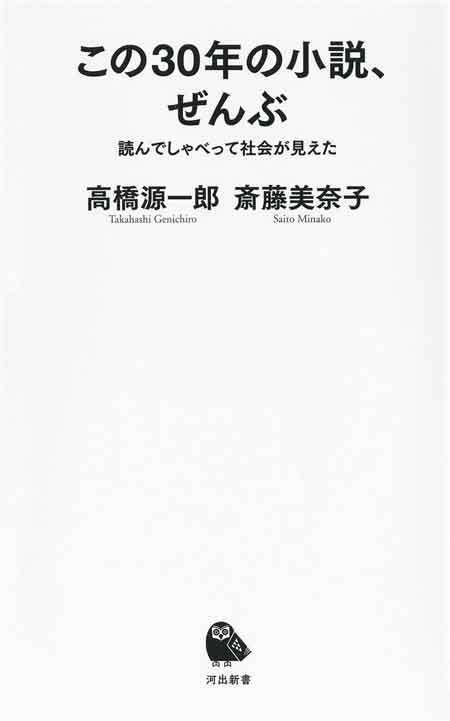
はたしてこの30年間、小説は、物語は、そして日本は、いったい何をやっていたんだろう。読んでいると、そんな問掛けを思わず自分のなかで飴玉のように転がしてしまう一冊である。
『この30年の小説、ぜんぶ 読んでしゃべって社会が見えた』は、小説家の高橋源一郎と、文芸評論家の斎藤美奈子による対談集である。対談が行われた時期は2011~2021年に跨る。なぜかといえば、「一年の終わりに、その年のベスト本を15冊ずつ持ち寄り、テーマごとに語ってゆく」という対談企画によって生まれた本だからだ。結果的に、日本の純文学を中心に、「平成」という時代の変化を追うことができる一冊となっている。
ふたりの会話は、ちょうど東日本大震災後からコロナ禍の小説に至るまでの年月と重なる。読んでいるといつの間にか「ああ確かに、当時ってそんな空気だったなあ」と、自分の記憶を辿っている人も少なくないだろう。
なかでも興味深いのが、「平成という時代を象徴する本」を選ぶ章である。高橋源一郎は「平成が終わるということは、単なる30年の時代が終わるというよりも、昭和から続く戦後の終わりを意味するのではないか」と述べる。確かに文学の世界を見渡してみれば、たとえば平成を代表する一冊として選ばれた桐野夏生の『OUT』(平成10年)は終身雇用制度に基づいた社会の崩壊を予感させ、なおかつ格差社会を予言する内容であった。あるいは朝井リョウの『何者』(平成24年)や村田沙耶香の『コンビニ人間』(平成28年)といった小説を読んでみても、明らかに昭和的な自分探しの時代が終わったことを感じさせる。文学には、確実に時代の空気が閉じ込められている。
しかし本書を読むと、文学の魅力とはある意味「時代の空気を曖昧に察知する」ことにあるのではないか、とも思えてくる。それはあくまで曖昧なのが、文学の魅力ではないか。
たとえば震災のことを、本当の意味で文学や評論という媒体のなかで「書ける」ようになったのには、実際に2011年から少し時間が掛かった。あるいは、コロナ禍のことを私たちがしっくりくる形で「物語る」ことができるようになるには、もう少し、時間を待たないといけないのかもしれない。
その遅延性は、今の時代において、むしろ貴重なものなのかもしれない……と思えるのだ。文学は、曖昧に時代の空気を捉えている。だからこそ、むしろ後から振り返ったとき、文学が誰よりも先にその次の時代をキャッチしていたりするものだ。本書を読むと、つくづくそう感じる。
この30年で、小説以外の娯楽――ネットフリックスもYouTubeもSNSも爆発的に流行った。今や小説以外の表現媒体はたくさんある。物語にしなくても、人は人の想いを、言葉を、たくさん受け取ることができる。
しかしそんな時代にあって、文学は、小説は、いったい何をやっていたのか、あるいはこれから何ができるのか。本書はそう問う。それは翻って、この社会がは何を言葉にしたいのか、を示す座標である気もするのだ。
(高橋源一郎・斎藤美奈子、河出新書刊、1078円税込み)

書評家 三宅 香帆 氏
選者:書評家 三宅 香帆
書店の本棚にある至極の一冊は…。同欄では選者である濱口桂一郎さん、三宅香帆さん、大矢博子さん、月替りのスペシャルゲスト――が毎週おすすめの書籍を紹介します。

















