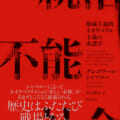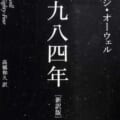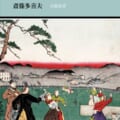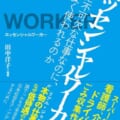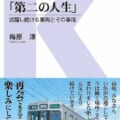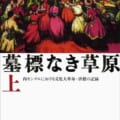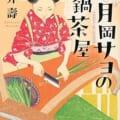【書方箋 この本、効キマス】第98回 『愛するということ』 エーリッヒ・フロム 著、鈴木 晶 訳/森岡 正博
現代の病理を映す名著
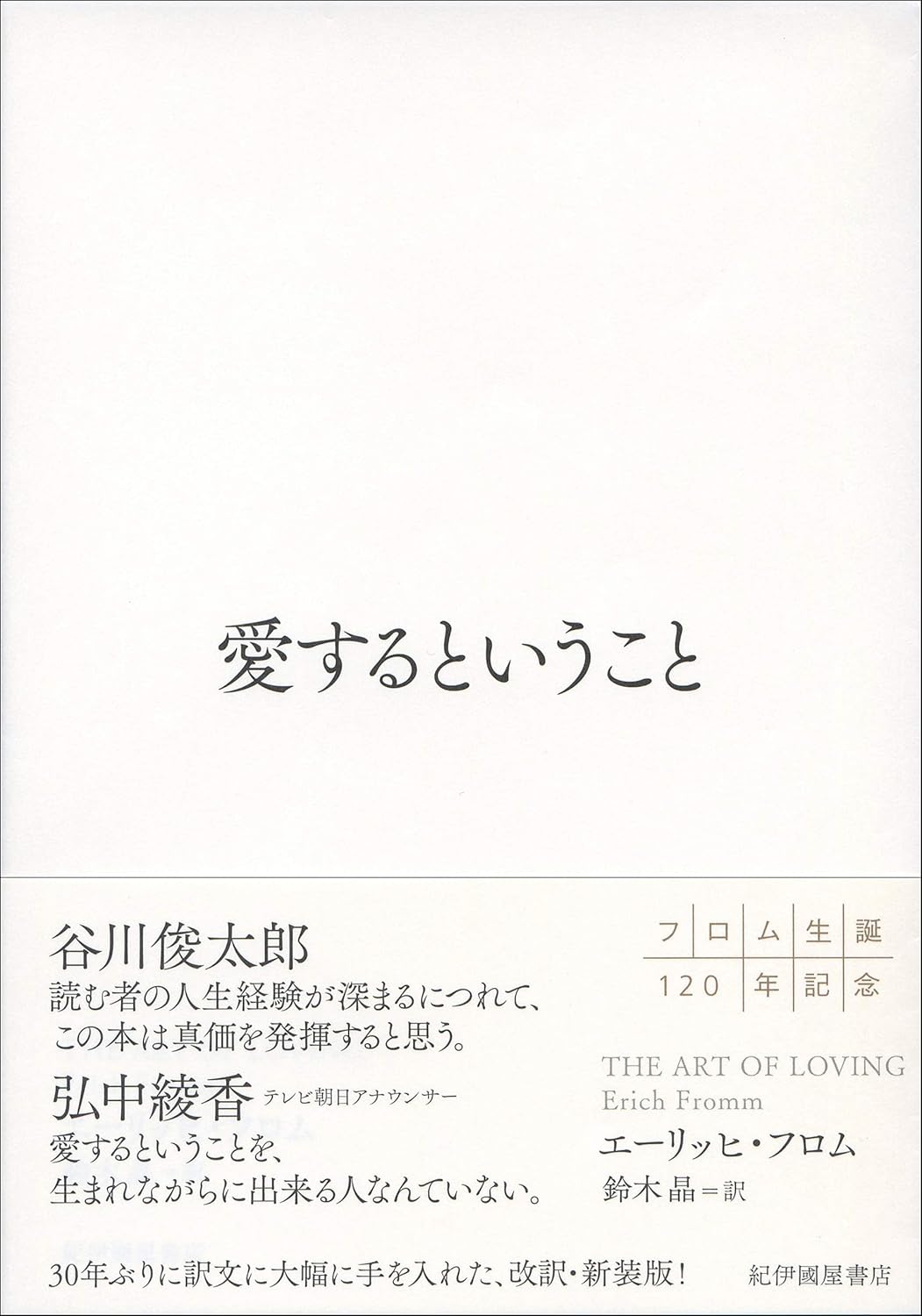
人を愛するとはどういうことだろう。紀元前の昔から、人々はこの問いを考え続けてきた。愛についての古典的名著はたくさんあるが、その中でも、社会心理学者のエーリッヒ・フロムが20世紀半ばに刊行したこの本は、現在も世界中で広く読まれ続けている。なぜならば、人生でいろんな体験をした大人の読者たちの知性に深く訴えかける内容となっているからである。
フロムは、自分の心に湧き上がってくる「君が好きだ!」という気持ちのことを愛とは言っていない。それは単に自分の気持ちが盛り上がっているだけのことであって、愛とは何の関係もない。愛とは、愛する相手が真の意味で幸せになるように願うことであり、そうなるように私が行動することである。愛とは相手の「成長と幸福を積極的に求めること」であるとフロムは言う。相手が自分の人生を肯定的に生きれるように、そして幸せな人生を送れるようにするために、私が相手にはたらきかけて共に生きていくことを、フロムは愛だと考えている。
フロムは、この考え方をさらに推し進めていく。人を愛するとは、私の中に息づいている生命を相手に与えることであり、その相手を「愛を与えることのできる人」へと変えていくことであるというのである。愛された人は、やがて自分が愛を与える人になって、さらに別の人へと愛を送るのだ。愛が愛を次々と生み出すこのようなダイナミックなはたらきを広げていくことで、現代社会のあり方を内側から変えていくことができるのではないかとフロムは考えている。
しかし、このような変革のパワーは、一歩間違えば、多くの人々を熱狂的な渦に飲み込んでいったり、「国のためなら私は死ねる」というような極端な自己犠牲を生み出したりしかねない。フロムはそのこともよく分かっていた。なにしろフロムは、ドイツのナチズムの熱狂から逃れて国外に出た思想家なのだ。力の強い他人や集団に自己を埋没させて肯定感を得るのは、フロムがもっとも嫌ったことだ。そもそも他人を愛するためには、まず人は自分自身の脚で精神的に自立していないといけない。そして自分の持っている良い面を好きになって、正しい自己愛を持たなければならない。自分の中心に支えられたしっかりとした自己肯定感覚があってはじめて、自分以外の人を愛することができるようになると言うのである。
自分の心の中にある孤独や不安や怖れから逃げるために他人を愛そうとしたり、国家と一体になろうとするのは、本末転倒である。しかし現代は、このような本末転倒の偽の愛が広がる時代でもあるのだ。フロムの鋭い分析は、まさに現代の日本社会の病理を見ている思いがする。誰かに愛されたいとひたすら願ったり、愛情を利用して他人を思い通りにコントロールしようとする行為が絶えない現在、本書はまさに必読であると言えるだろう。
(エーリッヒ・フロム 著、鈴木 晶 訳、紀伊國屋書店 刊、税込1430円)
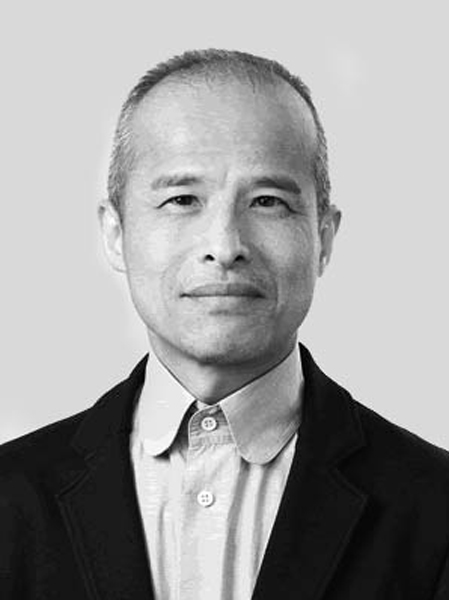
早稲田大学 人間科学部 教授 森岡 正博 氏
選者:早稲田大学 人間科学部 教授 森岡 正博(もりおか まさひろ)
哲学者。本紙では2007年に『無痛文明に生きる』を連載。著書に『人生の意味の哲学入門』など多数。
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。