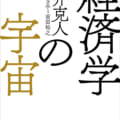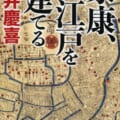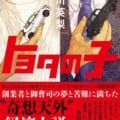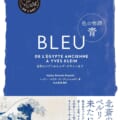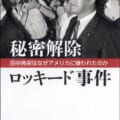【書方箋 この本、効キマス】第100回 『蔦屋』 谷津 矢車 著/大矢 博子
文化衰退にどう抗ったか
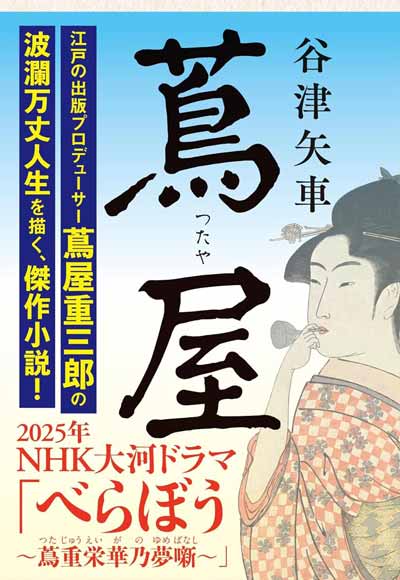
出版界の片隅に身を置くものとして、大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』を毎週興味深く観ている。江戸中期から後期にかけて活躍した版元で、本の企画・出版から販売まで取り仕切った蔦屋重三郎の物語だ。
ここまでの放送でも、「吉原細見」(吉原遊郭の案内)を売るために有名人の平賀源内に序文を貰ったり、遊女からの入銀(クラウドファンディングのようなもの)で「一目千本」という遊女の紹介本を作り、本屋には置かずに吉原でのみ配るというノベルティ戦略など、今でもやっている企画や販促が次々と登場する。大河ドラマといえばだいたい戦や政争が中心になるものだが、これは珍しいビジネス大河と言っていい。
吉原で育った重三郎は引手茶屋で働く一方、貸本業を営んでいた。ドラマではまだ吉原で暮らしているが、これから本屋の多い日本橋に打って出ることになる。そこからの重三郎の活躍を追ったのが、谷津矢車の『蔦屋』だ。
もともとは2014年、著者のデビュー2作目として刊行され高い評価を得た小説である。だが当時の版元が文芸から撤退したため文庫化されずにいた(他にも理由はあったようだが、詳しくはあとがきでどうぞ)。それが大河に合わせる形で、昨年10月に別の出版社で晴れて文庫化されたのである。ファンにすれば待ちに待った10年越しの文庫化だ。ありがとう大河ドラマ。
物語の語り手は日本橋の本屋、丸谷小兵衛。寄る年波には勝てず店じまいを考えていたとき、彼の店を買い取ったのが重三郎である。そして隠居するつもりだった小兵衛をを引き留め、ともに本屋をやってほしいと頼む。
絵師や戯作者をなだめたり脅したり、良い本を作ろうと奔走する重三郎。その情熱の源泉はどこにあるのか――というのが本書を貫く大きな軸だが、最大の読みどころは老中・松平定信が始めた寛政の改革のくだりだ。
時事を扱う戯作や浮世絵の禁止、過去に材を取りながら今を揶揄する内容の禁止。つまり政道批判はどんな形であっても許さないということである。さらに好色物も禁止、既刊は絶版が命じられた。それらを定めた触書はわざと曖昧な表現に終始しており、施政者次第でどんな解釈もできるという文章だ。
それに反したとして手鎖を受けた作家がいる。命を絶った者もいる。重三郎も莫大な罰金を払わされた。絵師も戯作者も本屋も萎縮し、摺師や彫師の仕事もなくなる。文化が政治によって衰退していく様子が実に恐ろしい。
そこで重三郎や小兵衛が何を思い、どう動いたかは本書でお確かめいただきたい。文化の灯を消さないという彼らの強い思いが、現代の豊穣なエンターテインメントの世界につながっているのだ。
なお、蔦屋に集った綺羅星のごとき絵師や戯作者の物語が読みたいという方には矢野隆『とんちき 蔦重青春譜』をお勧めする。まだ何者でもない若者たちが後のあの人たちになっていくという趣向が楽しい。こちらでも寛政の改革は大きな出来事として綴られる。戦ったすべての先人に心からの敬意を捧げたい。
(谷津 矢車 著、文春文庫 刊、880円)

書評家 大矢 博子 氏
選者:書評家 大矢 博子
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。