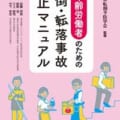【主張】シニア活躍も認定要件に
「健康経営」という日本語の名付け親であるNPO法人健康経営研究会(岡田邦夫理事長)は、健康長寿産業連合会および健康経営会議実行委員会とともに『「健康経営の進化」―2040年の日本の未来に向けて―』を発表した。少子化とともに避けられぬ課題である高齢化にスポットを当て、ワークエンゲージメント(I want to work.)の向上に留まらず、健康面にも配慮したヘルスエンゲージメント(I can work.)を伴わなければ、労働者と企業双方の成長を見込むことは難しいと訴えている。
総務省の労働力調査によれば、今年1月現在の就業者数は6779万人で、30カ月連続のプラスとなった。生産年齢人口(15歳以上65歳未満)が1995年をピークに減少し続けるなか、女性や65歳以上の就業率の向上が今も働き手の確保に貢献している。安全・健康面でクリアすべきハードルが高まるのは必然で、賃金格差の改善と並んで大きな課題となっている。
たとえば休業4日以上の死傷者数が最も多い転倒災害は、この10年で約1万件増加した。令和5年に死傷者数は3万6000人に達し、翌6年も速報値で前年同期比1.0%増(3万5850人=3月7日時点)という状況にある。容易に想像されるとおりシニア世代が被災するケースは多く、5年確定値のうちの45%が60歳以上で、50歳代まで含めれば全体の74%を占める。平均休業日数が48.5日に及んでいることを思えば、シニア世代までカバーし得るリスク回避策が欠かせない。
団塊ジュニア世代が65歳を超える2040年を見据えた同研究会の提言では、経営者が果たすべき役割として「自己管理能力が高い生涯現役の従業員を育成すること」を挙げる。さらに、定年を延長・廃止する動きが進むなかでは、「健康定年」といった概念を導入する必要性が高まることも想定される……などとしている。
経済産業省による健康経営優良法人認定制度では、認定法人が2万を超えた。シニアの活躍に直接つながるような項目が、認定要件に組み込まれることにも期待したい。