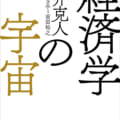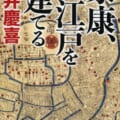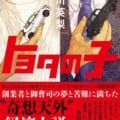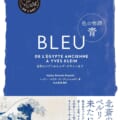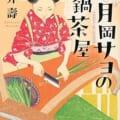【書方箋 この本、効キマス】第106回 『忍者の掟』 川上 仁一 著/山田 雄司
修行者のみが分かる嘘

本書は、現代に忍術を伝える甲賀伴党二十一代宗師家・川上仁一氏による自身の体験と、師から伝えられた「忍術」について解き明かした書である。
私が初めて川上氏に会ったのは、2012年に三重大学で忍者研究を開始したことに合わせて、『結Yui』という大学の雑誌の企画で対談したときだった。対談は伊賀の旧沖森邸の和室で行ったのだが、2時間ほどの間、川上氏はずっと姿勢を正して正座されていたことに、この人はただならぬ人物だと感じたのが最初の印象である。
それ以来、大学の授業、国内外の講演などで何度もご一緒させていただいているが、その精神的・肉体的両面における強靱さと柔軟さにはいつも驚かされている。まさに忍者に必要な「不動心」を体現していると言って良いだろう。
本書では、そうした川上氏がどのような修行をしてきたのか語られている。現代でこうした忍者修行をしたことのある人はほとんど皆無なので、忍者とはどのような存在かを知るうえでも大変貴重な記録である。
川上氏は6歳のころ、福井県遠敷郡瓜生村でハルピン特務機関に属したという石田正蔵と出会い、以来19歳に至るまで、甲賀流忍術の伴党忍之伝の教えを受け、忍術伝書や陰具、伝来の由緒書・家系図などをすべて受け継いだ。修行の内容は、幼児期、児童期、少年期、青年期と成長するに随い、より高度に複雑になっていった。
修行については、忍術書に記されずに師から身をもって伝授されることが多く、この世界に入らないと分からないので、大変貴重である。たとえば、「悪食の鍛練」として、縁の下に何日も潜んでいなければならないとき、土は腹の足しになるということで、土や動植物も食べたという。また、砂利の中に手指を突き込んで鍛える「虎之爪」や、全身を鉄棒でくまなく打つ「骨固め」などの過酷な修行を行った。こうした川上氏の修行の様子については、1988年にNHK北陸東海「若狭の鉄人~甲賀流忍者・川上仁一~」として放送されたことがある。
しかし、川上氏の特徴的なところは、「忍者はこんなに素晴らしい」などと誇るのではなく、秘伝書や伝承には嘘も多く、「忍術はこうあるべきだ」という理想論で書かれた部分も多々あると客観視している点である。これは実際に忍術修行をしてきた人でなければ言えないことである。
また、本書では、世に知られていない川上氏しか所蔵していない伝書の紹介がされていることも貴重である。福井藩でテキストとして用いられたという「義経流陰忍伝」や、織田勢の大規模攻略を察知して天正7(1579)年伊賀衆が雨乞山の山砦に籠城して団結を図った際に交わした「雨乞山籠城掟書」などは、初めて紹介された貴重な内容である。
忍者・忍術はいまもって分からないことが数多くある。本書はその一端を垣間見ることができる貴重な書である。
(川上 仁一 著、角川新書 刊、税込990円)

三重大学 人文学部 山田 雄司 氏
選者:三重大学 人文学部 山田 雄司(やまだ ゆうじ)
忍者学研究の第一人者で、国際忍者研究センターの副センター長。著書に『忍者の歴史』など多数。
濱口桂一郎さん、大矢博子さん、そして多彩なゲストが毎週、書籍を1冊紹介します。“学び直し”や“リフレッシュ”に是非…。