【見逃していませんか?この本】「わからなさ」と末永く付き合うための戦略/森達也『私たちはどこから来て、どこへ行くのか 科学に「いのち」の根源を問う』
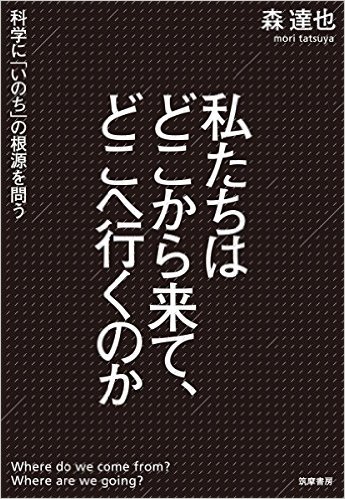
本書のタイトルは、ゴーギャンが南洋のタヒチ滞在時代に描いた有名な絵画作品の題名から取っている。
その絵画には、重要な意味を持つ3種類の人物が配置され、「人生の始まり」「成年期」「老年期」にそれぞれ対応している。そして「老年期」を意味する老女の足元には、奇妙な白い鳥がいて、「言葉の無力さ」を物語っているという。これは本書の語り口とも響き合うものだ。
森達也は、ドキュメンタリー作家として知られる一方で、評論、小説を問わず旺盛な執筆活動を行っている。そんな森が長年抱えていた疑問を、福岡伸一、池谷裕二、諏訪元、村山斉などの第一線で活躍する科学者たちに率直にぶつけていく。ときにその「なぜなぜ」はあまりに本質的過ぎて、DNAのらせん構造のようにグルグル回った挙句、巨大な謎の中に呑み込まれそうになる。「人はなぜ死ぬのか」「宇宙はどうなってしまうのか」等々の大きなテーマと、最先端の学問的成果が終わりのない問答を続ける摩訶不思議な会話劇なのだ。
森は、生物学者・福岡伸一との対談で、小学校に入る前後の時期に「死という概念を初めて知って、自分でも制御できないほどの恐怖に襲われたこと」を述懐する。それは、死によって自分が消えてなくなることの意味が「わからないと思う自分の存在が消えることの意味がわからない」という恐怖の堂々巡りである。両親にこの恐怖を訴えても、死ぬことは眠るようなものだとかわされる。だが、森は納得しない。「なぜなぜ」は止まらない。
森はそれを「足掻き」と表現する。しかし、それにも限界がある。
そこで、森がとったスタンスは明快だ。「わからないことを無理にわかろうとしないほうがいい」だ。
個々の細胞は凄い速度で死んでおり、それゆえ記憶も絶え間なく更新されている。だとすれば、記憶は保存されているというよりも、毎回再生されているから保存されているかのように錯覚しているだけで、しかも再生のたびに少しずつ変容しているかもしれない……。そんな福岡の記憶をめぐる仮説に、森は、「わからないこと」の「理由や意味を無理に解釈しようとしても仕方がない。いやむしろ過ちの元だ」というメッセージを読み取る。
これは「わからないこと」は一切考えないということではない。「わからなさ」と末永く付き合うための人生の知恵であり、戦略である。
それはまるで、はっきりした答えばかりを求めてさまよい、道標を探すことでかえって迷子になっている、今の私たちに対するアンチテーゼのようでもある。(N)
◇
もり・たつや、筑摩書房・1620円/作家、映画監督。『いのちの食べかた』『A3』『それでもドキュメンタリーは嘘をつく』『神さまってなに?』など


















