- 2022.07.02 【書評】
-
【今週の労務書】『70歳就業時代における高年齢者雇用』
人事制度の影響を分析 近年の高年齢者雇用安定法の改正を受けて、65歳以降の雇用・就業に向けた現状と課題を明らかにするべく、複数の統計データやアンケート調査を活用し、分析した。同法改正や在職老齢年金の見直しが企業に与えた影響を俯瞰しつつ、70歳までの継続雇用を前提とした人事制度設計の参考になる知見を得ることができる。 とくに定年後の継続……[続きを読む]

人事制度の影響を分析 近年の高年齢者雇用安定法の改正を受けて、65歳以降の雇用・就業に向けた現状と課題を明らかにするべく、複数の統計データやアンケート調査を活用し、分析した。同法改正や在職老齢年金の見直しが企業に与えた影響を俯瞰しつつ、70歳までの継続雇用を前提とした人事制度設計の参考になる知見を得ることができる。 とくに定年後の継続……[続きを読む]

労働新聞社Webサイトに2021年に掲載した記事で、2021年下半期にアクセス数が多くよく読まれている人気の記事を再紹介していきます。 2021年8月9日掲載【助成金の解説】 令和3年4月1日改正高年齢者雇用安定法を推進 少子高齢化社会の急速な進行により、労働力の大幅な減少が見込まれています。高齢者が社会の担い手として期待される中、令和……[続きを読む]

令和3年4月1日改正高年齢者雇用安定法を推進 少子高齢化社会の急速な進行により、労働力の大幅な減少が見込まれています。高齢者が社会の担い手として期待される中、令和3年4月より改正高年齢雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲があれば65歳以降でも働ける企業が増えることが重要な課題とされています。……[続きを読む]

令和3年4月からは、改正高年法が施行され、事業主は70歳までの就業機会確保に向けた体制整備が求められます。 現行の高年法では、「希望者全員65歳まで継続雇用(経過措置付)」を義務付けています。経過措置は令和6年度末で終了ですが、今回の改正は、企業側にその「一歩先」の対応を促すものです。具体的には、令和3年4月以降、事業主が就業確保を図……[続きを読む]
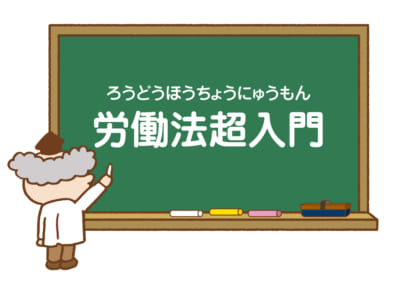
70歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする改正法案、いわゆる「70歳定年法」が閣議決定された。 2004年の高年齢者雇用安定法改正では、65歳までの雇用確保措置の導入が求められ、企業は「定年の廃止」「65歳までの定年延長」「継続雇用制度(いわゆる再雇用)の導入」のいずれかを実施してきた。しかし、現場では定年後の処遇変更や役職定年に……[続きを読む]

はご利用いただけません。