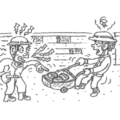【人事学望見】第1313回 偽装請負と雇用義務 黙示の労働契約成立したと争う

デキちゃった婚と似てる?
人材ビジネス会社から、人材を受け入れる際、派遣または業務請負という選択肢がある。2つの仕組みは一長一短だが、両者の「いいとこどり」を狙うのが、いわゆる「偽装請負」だ。しかし、これが露見すれば当然、ペナルティーを受けることになる。
最高裁判決まで紆余曲折
現在、偽装請負と判断されれば、派遣法の規定により、法に反する派遣先は派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなされる(労働契約申込みみなし制度)。結果として、派遣を受けていた労働者を直接雇用せざるを得ないことになる。
これは、平成24年改正法で設けられた規定(施行は3年後)だが、偽装請負の抑止策という意味では、なかなか効果が高いと評価されよう。このペナルティーの重さを実感していただくために、法改正前の判例の流れを振り返ってみよう。
派遣法の要件を満たさずに、人材を受け入れ、安価な労働力として利用する企業に対して、労働者サイドが「実質は直接雇用の労働者と変わらず、黙示の労働契約が成立していた」などと主張して、裁判が争われるようになった。
人材の受入れ先と労働者の間で黙示であっても労働契約が成立していれば、それは派遣の枠から外れ、職業安定法で禁止する労働者供給に該当することになる。
しかし、派遣法違反なら、そのことだけで、労働者供給に当たるという理屈は、いささか「直線的」過ぎるともいえよう。
この微妙な問題をめぐって、解決の枠組みを提示したのが、最高裁の判決(パナソニックプラズマディスプレイ〈パスコ〉事件=最二小判平21・12・18)だ。事件の経過は複雑だが、争いの焦点は、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら