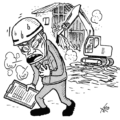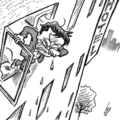【社労士が教える労災認定の境界線】第375回 家事住み込み業務後に心筋梗塞
災害のあらまし

介護福祉士のXは、訪問介護事業・家政婦紹介あっせん事業などを営むY社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、家事業務や介護業務に従事していた。Y社のサービス利用者であるZ宅で家政婦兼訪問介護ヘルパーとして働いていた他の家政婦が休暇を取得している間、Xは代替要員としてZ宅に住み込み、家事業務と介護業務に従事した。
7日間の住み込み業務を終えた後、Xは某市内の入浴施設に立ち寄ったが、その日の深夜に施設内のサウナで倒れているところを店員に発見された。救急搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は急性心筋梗塞または心停止と診断された。
判断
Xの遺族は管轄の労働基準監督署に対し、Xの死亡はY社の業務に起因するものとして労災保険法の遺族補償給付と葬祭料を請求した。しかし労基署は、Xは労災保険法が適用されない「家事使用人」に当たるとしてそれらを不支給とした。Xの遺族はその処分を不服とし、労災保険審査官への審査請求および労働保険審査会への再審査請求を行ったが、いずれも棄却された。
Xの遺族は不支給処分の取消しを求めて訴訟を提起。地裁での第一審は、Xの家事業務がZの息子との間で結ばれた家政婦としての雇用契約の下で行われていたことや、Y社との契約に基づく訪問介護サービスに係る業務が過重とまではいえなかったことなどを理由に遺族の請求を棄却した。しかし高裁での控訴審では、Z宅での家事業務および介護業務が一体としてY社の業務であることと、7日間ほぼ休みなく住み込みで働いたことが「短期間の過重業務」に当たることからXの死亡に業務起因性を認め、業務上と判断された。
解説
労災保険法は業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡などに対して必要な保険給付を行うための法律だが、ここでいう「労働者」とは…
執筆:一般社団法人SRアップ21 宮城会
社会保険労務士事務所たすく 代表 中島 文之
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら