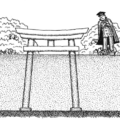【国土を脅かす地震と噴火】10 平安時代の富士山② マグマ満ち噴煙立ち昇る/伊藤 和明

不死の霊薬を高き山で燃やす
イラスト 吉川 泰生
平安時代は、富士山の活動が最も激しかった時代だけに、当時の文学作品には、活動する富士山の姿を描いたものが少なくない。
平安時代初期の漢詩人である都良香(みやこのよしか)は、実際に富士山頂に登り、『本朝文粋(もんずい)』の第十二巻に、「富士山記」という一文を載せていて、当時の山頂火口の模様を知ることができる。
「此の山の高きこと雲表(うんぺう)を極めて、幾丈といふことを知らず。頂上に平地あり、広さ一里ばかり。其の頂の中央は窪み下りて、体炊甑(かたちすいそう)の如し。甑(こしき)の底に神(あや)しき池あり。池の中に大きなる石あり。石の体驚奇(かたちきやうき)なり、宛(あたか)も蹲虎(そんこ)の如し。亦(また)其の甑の底を窺へば、湯の沸き騰(あが)るが如し。其の遠きにありて望めば、常に煙火を見る」
ここに記された“蹲虎”、つまりうずくまっている虎に似た大石は、現在も山頂の火口底にあって、“虎岩”と呼ばれている。
平安時代後期の著名な女流文学作品である『更級日記』にも、噴煙を上げている富士山の姿が描かれている。作者である菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)は、1020(寛仁4)年の秋、上総から京へと帰任する父に従って、駿河の国に入った。
「富士の山はこの国なり。わが生ひ出でし国にては、西おもてに見えし山なり。その山のさま、いと世に見えぬさまなり。さまことなる山の姿の、紺青(こんじやう)を塗りたるやうなるに、雪の消ゆる世もなくつもりたれば、色濃き衣(きぬ)に白き衵(あこめ)着たらむやうに見えて、山の頂の少し平らぎたるより、けぶりは立ちのぼる。夕暮れは火の燃えたつも見ゆ」
作者は、当時12~13歳の少女だったが、新雪をまとった富士の姿と、山頂から絶えず噴煙が上がり、夜には赤々と燃え立つさまが巧みに描かれている。恐らくこれは火映現象であろう。もしそうであるならば、山頂火口にはマグマが満ちていて、溶岩湖になっていた可能性もある。
かぐや姫の物語で知られる『竹取物語』にも、終局の場面で富士山が登場する。月からの迎えの車に乗って、かぐや姫は月へと帰っていくのだが、そのとき姫は、帝への置きみやげとして不老不死の霊薬を残していく。しかし、寵愛していた姫に去られた帝にしてみれば、そのような霊薬など何の価値もない。
そこで帝は、不老不死の霊薬を駿河の国にあるという高い山の頂に持って行き、火を付け燃やすよう勅使に命令する。
「そのよし承りて、士(つわもの)どもあまた具して、山へ登りけるよりなむ、その山を『富士の山』とは名づけける。その煙、いまだ雲の中へ立ち昇るとぞ、言ひ伝へたる」
不死の霊薬を焼いた煙が今も立ち昇っているのが、富士山の噴煙なのだと言い伝えているのである。
『竹取物語』については、作者も成立年代も不明なのだが、仮名文字の成立や用語の使い方などからみて、9世紀末~10世紀初頭にかけての作ではないかと推測されている。
このように、平安時代の文学作品は、富士の山頂から絶えず噴煙の上がっていたことを物語っている。
筆者:NPO法人防災情報機構 会長 元NHK解説委員 伊藤 和明
|
〈記事一覧〉 |