- 2023.06.29 【労働新聞】
-
【ぶれい考】欠かせぬ高度外国人材/近藤 宣之
少子高齢化による人手不足が深刻化するなかで、労働力の長期的確保は、今や国の存立上の重要な課題となっている。これまで、労働力の確保と、人財育成を通じた国際貢献のために、一定の役割を果たしてきた技能実習制度および特定技能制度は現在、見直しの議論が進む。その方向性は、日本で働く外国人の能力を最大限発揮できる制度であり、日本の深刻な人手不足の緩……[続きを読む]

少子高齢化による人手不足が深刻化するなかで、労働力の長期的確保は、今や国の存立上の重要な課題となっている。これまで、労働力の確保と、人財育成を通じた国際貢献のために、一定の役割を果たしてきた技能実習制度および特定技能制度は現在、見直しの議論が進む。その方向性は、日本で働く外国人の能力を最大限発揮できる制度であり、日本の深刻な人手不足の緩……[続きを読む]

労使双方に義務がある 健康経営とは従来の産業保健(労働衛生)と福利厚生の考え方を発展させたものであり、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」である。会社の理念に基づき従業員の健康増進に投資することは、医療費負担の軽減だけでなく、従業員の活力や生産性の向上を通じた組織の活性化をもたらし、業績や株価の向上につながると……[続きを読む]

賃金格差は146国中75位 ジェンダーギャップ指数は、経済・教育・保健・政治の分野ごとに各使用データをウェート付けして算出している。男女が完全に平等な状態を100%とした場合の、全世界の達成率は68.4%で、昨年度より0.3ポイント上昇した。 日本は64.7%で、対象の146カ国中125位だった。昨年の116位から大きく順位を下げ、過……[続きを読む]
裁判例は手当が中心 パートタイム・有期雇用労働法のいわゆる同一労働同一賃金規定は、2020年4月に大企業、21年4月に中小企業への適用が始まった(派遣労働者については、20年4月施行)。これまでこの規定や旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)に基づき裁判で不合理と認定された例は手当が中心で、基本給の差を不合理とした例はほとんど存……[続きを読む]

原則の記入は必要に 厚生労働省は、令和4年1月7日、「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(以下「シフト制留意事項」という)を公表した。 シフト制という働き方自体は、労働日および労働時間の柔軟な設定という観点から労働者と使用者の双方にメリットがあり得るものであるという理解を前提としながらも、使……[続きを読む]







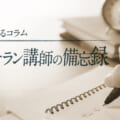








はご利用いただけません。